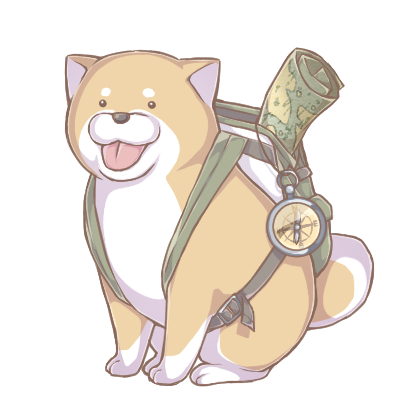今年の夏は、暑い。
うだるような暑さの8月、ぼくは京都にいた。
半年ぶりに祖母の家の引き戸を開けると、懐かしい鈴の音と、懐かしい町屋の香りがぼくを包む。ぼくは、京都に帰ってきた。
いつも通り、甲子園の実況を聞きながら、祖父の淹れる自慢の珈琲をすする。どこかの強豪がサヨナラ負けしたらしい。居間には、ぼくと祖父の2人。2人だけだ。
体調を崩した祖母は、ここ1か月間寝込んでいた。
痩せ細った手足にふと目が行く。
ぼくは、控えめな声で「ただいま」を言う。
就職が決まったこと、東京での暮らしはうまくいってること、
いつも通り、ぼくはいろんな話を聞かせてあげる。
「なぁ、爪、伸びてきてん。切ってくれへんか?」
唐突に祖母が呟いた。
数年ぶりに握る祖母の腕は、やっぱり細くて、壊れそうだった。
硝子の置物を触るように、ゆっくりゆっくり、爪を切る。
そうか、自分以外の爪を切るのは初めてだ。
祖母は腕を上げ、電球に手を透かして、天井を見上げる。
「ほんまに、優しいええ孫に恵まれて良かったわ。ありがとうなあ。ほんまに、ほんまに、ありがとうなあ。」
涙が止まらなくなった。
涙を隠しながら、僕は言う。
「ちょっと昼寝するわ、おばあちゃん。」
腕の間から涙が零れて、畳を濡らす。
ぼくは、祖母になにをしてあげられたのだろうか。
これまで、祖母になにをしてあげられたのだろうか。
うつ伏せの腕には畳の跡が強く残っている。
懐かしい駅で、乗り慣れた電車がブザーを鳴らして出発する。
今年の帰省はいつもより、荷物が重い。
喉の奥には、祖父の珈琲の苦味がまだ残っていた。
そうだ、実家帰ろう
年末年始やお盆休みなどの大型連休が近づくと、帰省のためのチケットを取る。地元を離れてから、お盆と正月に帰省しなかったことは一度もない。
年間に2回、5日ずつ帰省すると、年間10日間。
親があと20年生きられるとすると、20×10日で計200日間。
親にはあと、たった200日間しか会えないのだから。