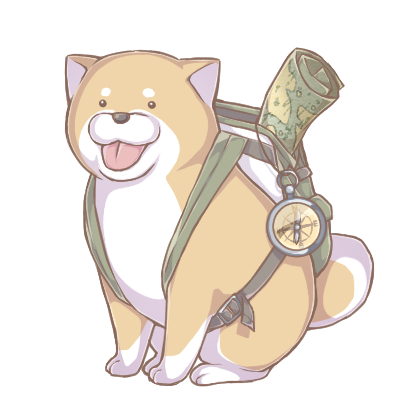3月1日から2019卒の就職活動が解禁になりましたね。
僕は14卒で就活をしているのでもう5年も前になるのですが、リクルートスーツを着た不安そうな表情の学生を見ると未だに当時のことを思い出します。めちゃめちゃ大変だったなあ。。
ここ数年は売り手市場で学生に有利なんて言われておりますが、就活生はそれでも不安なもの。本日は同じく苦労をしてきた少し年上のおっさんが、就職活動における戦略について語りたいと思います。
もちろん個人の経験に依拠している部分は大きいので、絶対的な正解ではないかと思いますが軽い気持ちで参考にしてもらえれば幸いです。
Contents
面接やESでよく聞かれたことランキング
まずは僕の就活を振り返って、よく聞かれたことランキングについて紹介してみましょう。某人材会社やキャリアセンターなんかはやれ自己分析だやれ業界研究だと色々うるさいですが、就活で質問されることはほぼ決まっています。
これらの質問に明確なロジックと熱意を持って答えることができたら意外と内定は貰えるものです。まあ、そのロジックを作るのに自己分析や業界研究も多少は必要になるのですが。
3位:あなたの研究内容・勉強内容について教えてください
理系であれば頻出の質問でしょう。僕は文系だったのでそこまで多く聞かれることはありませんでしたが、就活の中でどんな勉強をしてきたのかを伝える場面は必ずあります。
その分野について詳しくない人に対して分かりやすく説明・プレゼンできる内容は準備しておきましょう。僕はそれほど勉強熱心な学生ではありませんでしたが、自分が学んでいる分野のさわりくらいは説明できるようにしていました。
2位:志望動機について教えてください
続いては志望動機。これは大抵の企業で聞かれます。とは言っても、皆が「御社が第一志望です!」なんて言うのであまり重要視されている感じは受けませんでした。一応聞いておくか、みたいな。
ただし最低限「なぜこの業界を選んだのか」「その中でなぜこの企業に入社したいと思っているのか」ぐらいはきちんと説明できるようになっておきましょう。いわゆる「就活における軸」というのはちゃんと持っておいた方がいいです。
1位:学生時代頑張ったことについて教えてください
そして堂々の第1位はこれ!聞かれなかった会社はほぼありません。「これまでの人生で熱中したことを教えて」「学生時代打ち込んだことは何?」など色んなバリエーションはありますが、結局はあなたがこれまでの人生で一番頑張ったことって何?という質問です。
ES・面接含めてほとんどの企業でまず間違いなく聞かれます。なので入念な準備をしておきましょう。本日の記事のメインはこの「学生時代頑張ったこと」に対して考察していきたいと思います。
「学生時代頑張ったことを教えてください」という質問で面接官は何を見ているのか
就活において頻出のこの質問。どこの企業でも聞いてくるのには何か理由があるはずです。その背景について考えたことはありますか?
僕は「学生時代頑張ったこと」について深掘りすることによって、①その学生の基礎的な能力・②その学生の強みや性格が分かるから、だと考えています。
「強みは何ですか?」とわざわざ聞いても、この画像のような展開になることは目に見えています。

こんな馬鹿げた会話をすることもなく、その学生が打ち込んできたエピソードを聞けばその学生の強みや性格を把握することが可能ですし、何より具体的なエピソードの深掘りになってくるので、学生も嘘をつくことができません。
それではこの「学生時代頑張ったこと」に対する答え方について、意識すべき点をお伝えしましょう。
注意すべき点はエピソードの「レベル感」
これまで後輩やココナラで数十人のESを見てきましたが、エピソードのレベル感が低い就活生がほとんどです。レベル感をあげることを意識するだけで驚くほどESや面接の質が変わります。
レベル感が低い、というのはどういう意味かというと「え、当たり前じゃん…」というエピソード。自分は頑張ったことをきちんと書いているつもりなのに、客観的に見ると非常にレベル感が低いケースが多々あります。
例えば、こんなケース。
カフェでアルバイトをしていて、最初は何度もミスをしてしまい、店長から怒られてばかりで悔しい気持ちでいっぱいでした。そこで失敗をしないように、①教わったことに対してはメモをきちんと取ってマニュアルを作成すること、②疑問に思ったことは何でも先輩や社員に確認をすることを徹底するようにしました。これらを意識した結果、ミスのないオペレーションをすることができるようになりました。この経験から「失敗から学び、改善する力」を身に着けられました。
どうでしょうか?こんなES、書いてしまいがちではありませんか?
言いたいことはよく分かりますし、素直にバイトをしていた実直な人柄も伝わります。しかし、、これでは社会人にとっては「当たり前」なエピソードで響きません。
マニュアルを作成し、疑問点を解決し、仕事を進めていく、というのは社会人としてはできて当たり前のことであり、それをアピールしても「この人材が欲しい!」とは思ってもらえないのです。
このようにエピソードにはレベル感というものが存在します。
以下に、それぞれのレベル感について解説していきます。
レベル①受動:言われたことがきちんとできる
まずは「受動」の段階です。これはカフェのバイトで言えば、店長から指示をされたことをミスなくこなし、問題なく仕事を回せる状態のことです。
面「バイトではどんなことを頑張りましたか?」
就「そうですね、とにかく店長から言われたことや教わったことはしっかりとミスなく行えるように頑張りました。」
面「なにかその中で工夫などはしましたか?」
就「工夫ですか…。特にないですね。とにかくミスしないことを意識して頑張りました」
さすがにこのレベルの受け答えで面接に臨む人は少ないかとは思いますが「言われたことはまあ忠実にこなせるのかな」というレベルで認識されます。恐らくこのレベルでは内定を取ることは難しいでしょう。
レベル②能動:言われなくても自分で行動できる
続いては「能動」の段階です。先ほどの例で言えば、マニュアルを作成したり、疑問点を自発的に解決したりと自分から行動できる状態です。
面「バイトではどんなことを頑張りましたか?」
就「そうですね、最初はミスが多かったので自分でマニュアルを作成してミスをしないように心掛けました。またオペレーションやメニューでも気になったことがあれば先輩に確認するようにして、自らがスキルアップできるように行動していきました」
最初にあげた例がこちらの「能動」ゾーンに分類されます。面接官からは「言われたことに加えて、自分で考えて行動しているな」と認識されるでしょう。
レベル③能動+一般的工夫:自分で行動しながら、工夫する力がある
続いて「能動+一般的工夫」の段階です。能動的な行動に加えて、自分なりに工夫して改善をしていける人材になります。
面「バイトではどんなことを頑張りましたか?」
就「バイトにおけるマニュアル作成です。閉店時の店締め作業で、バイトによるミスが多発していて、翌朝の開店に支障が出て開店時間を遅らせるという問題が何度もありました。」
面「へえ、大変だね。それで、どうなったの?」
就「はい、私は当時ベテランのスタッフだったので、店長からこの問題の解決を任されました。そこでまずはどんなミスが多く発生しているかミスの種類を分類しました。そして、それらのミスについて注意喚起の張り紙を事務所に張ったり、丁寧なマニュアルを作成して店に置くようにしました。結果、ミスはかなり削減することができました。」
問題に対して自分なりに分析し、簡単ではあっても対策を立案して実行し、実際に効果を出しているということは評価されるでしょう。面接官からも「自分で考えて動き、工夫もできる子だな」と認識してもらえます。
レベル④能動+創意工夫:自分で考え、行動し、創意工夫できる
続いては、「能動+創意工夫」の段階です。レベル③よりも高度な創意工夫ができる人材です。
面「バイトではどんなことを頑張りましたか?」
就「はい、カフェの売り上げを上げるための新規商品の企画に挑戦しました。」
面「新規商品?どんな商品をつくったの?」
就「はい、当時カフェの売り上げが少し傾いていて、店長に対して新規商品の提案をしました。最初に考えた商品は却下されてしまったのですが、それが悔しくてお客さんにアンケートを取ったり、周囲のカフェで提供されている商品を分析したりして、お客さんが本当に求めているスイーツを1か月かけて考えました。特にアンケートはExcelを使って分析し、分かりやすいグラフにして店長に再提案したところ、採用してもらえることになりました。その商品の評判は上々で今では店の売り上げを支えるメニューの1つになり、客単価の向上に貢献することができました。この経験から自分で物事を分析して売れるものを提案していくことに楽しさを感じるようになりました。」
能動的に動きつつ、高度な創意工夫を加えて結果を出せる人材ですね。面接官からも「行動することだけでなく、自分で創意工夫までできるのか」と認識してもらえます。
レベル⑤能動+創意工夫+周囲の巻き込み:自分だけでなく周囲の人間を巻き込み成果を上げられる
最後は「能動+創意工夫+周囲の巻き込み」の段階です。レベル④の工夫に加えて、周囲も巻き込みリーダーシップを持って行動できる人材です。
面「バイトではどんなことを頑張りましたか?」
就「はい、学生だけでカフェの立ち上げに挑戦しました」
面「カフェの立ち上げ?どんなことをしたの?」
就「もともとはカフェでアルバイトしていたのですが、友人5人と学生だけで新しくカフェを開きたいと思い、学生だけでカフェの立ち上げに挑戦しました」
面「資金とか、物件とか、宣伝とか、バイト集めとかいろいろと大変じゃなかった?」
就「はい、大変でした。特に資金集めは一向にお金を集めることができず苦労しましたが、SNSなどで宣伝しながら友人に1口1万円から出資を募り、出資者はコーヒーを1週間に1回無料サービスをするという仕組みを作りました。またより多くの出資者を集めるためにチラシを作成したり、自分が自ら学内のフリーペーパーを作成している団体などに営業に行き、計3紙のフリーペーパーで宣伝してもらえることになりました。実際にオープンする段階では、バイトを集めるのに苦労をしたのですが…」
能動的に動き、工夫し、さらに他人を巻き込みながら大きな成果を上げることができる人材ですね。面接官かも「この子は面白い、行動してさらに他人を巻き込んで成果まで上げられるのか」と感心してもらえます。
重要なのは、問題に対して何を考え、どんな行動を起こしたか
エピソードのレベル感について見てきましたが、納得いただけたでしょうか?そして自分のエピソードはどのレベルに位置するものでしたか?
企業によって評価基準は様々だと思いますが、私が面接官だったら、レベル①の人材よりはレベル③~⑤の人材の方が話を聞いていても面白いと思いますし、自分の会社に入社した後も活躍してくれるイメージが持てそうです。
この「イメージ」というのは非常に重要です。
「再現性」と言い換えてもいいかもしれませんが、自分の企業に入社した時に、この子なら学生時代みたいに「自分できちんと考えて行動してくれそうだな」と思ってもらう ことが重要と言って良いでしょう。
まとめ
エピソードの「レベル感」について意識をしながらESや面接に臨むことで内定をもらえる確率はぐっと上がります。就活は準備が命です。色んな人に客観的に見てもらいながらエピソードを洗練させていきましょう。
僕も含めココナラでは「ES添削サービス」を出品している人が多くいます。周囲にESを見てもらえる人がいない場合は、是非こちらを利用してみてはいかがでしょうか。
就活はまだまだ始まったばかり。色々と悩むことも多いかと思いますが、自分を信じて頑張ってください!